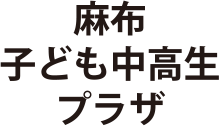活動の
記録
2018年04月02日
「麻布探検」~わらしべ長者で物々交換~
3月30日の金曜日に、昔話『わらしべ長者』をモチーフに、
街の方々と物々交換を行うプログラム、麻布探検を行いました。
小学生13名で麻布商店街へ行き、商店街で働く方々や街で過ごしている
方々に声をかけ、物が変わっていく過程や街の方々との
やりとりを楽しみました。
3つのグループにわかれ、最初はとても小さな[シール]
からのスタートです。
普段はあまり入ることのないお店に入ってみたり、
街を歩いている人に突然話しかけてみたり、
と初めての経験に子どもたちの心はドッキドキ・・・。
緊張しながらも頑張って話しかけ、やさしく答えてくださると、
子どもたちは安心したようでした。声をかけていくうちに、
少しずつ話しかけることになれて、
積極的に活動している姿が見られました。
交換していくものすべてが子どもたちにとって魅力的で、
キラキラした眼差しで、楽しんでいました。
1時間半の活動を楽しんだ後は、
プラザへ戻ってグループごとに発表を行いました。
最初のものから、こんな風に変わっていきました、という発表の中で、
「このお店ではこんな話を教えてくれました!」
「こんな風に思ったからこの人に話しかけてみたんだよね!」
などたくさんのエピソードを聞くことができました。
今回は、物々交換という手段を通して、普段自分達が暮らしている街に、
「こんな素敵な人が働いているんだ!」
「こんなお店やこんな場所があったんだ!」
と興味や関心を持つきっかけとなり、自分の街へ愛着を持つことを
目的にプログラムを実施しました。
あるお店では、「交換できるようなものはないんだけどね・・・。」
と言いながら、「このお店は80年前にできたお店で、
その頃の日本は戦争中だったんだよ。僕はその頃小学生でね・・・。」
と、お店の歴史や戦争での体験を教えてくださる方もいました。
子どもたちはとても驚いたようで、その後もほかのお店を回る中で、
「このお店は、何年くらいやっているんですか?」
などお店の方との会話のやり取りを楽しむ様子が見られました。
お仕事中にも関わらず、やさしくあたたかい対応を
してくださった地域の方々、ご協力いただき、
ほんとうにありがとうございました。
緊張した気持ちで話しかけ、地域の方々に優しい言葉を
返していただけたこと、こうしたあたたかな体験が
子どもたちの心の中に残ったことと思います。
以下に、子どもたちの交換の記録を載せさせていただきます。
【グループ1】
シール→ボールペン(TAKEMASAさん)→折りたたみ傘(KUROSUGALLERYさん)
→ハートのふうせん(ながとやさん)→沖縄土産のお魚マグネットとひざ掛け
(静屋家具センターさん)→ハローキティのぬりえ(HIRANOYAさん
)→コップ(FRIJOLESさん)
【グループ2】
シール→万華鏡(カレイドスコープ昔館さん)
→マーガレット、お花(だんだんばたけさん)→ポーチ(ケーワイ堂靴店さん)
→サングラス(PARISMIKIさん)→黒猫のぬいぐるみ(Tinker Bellさん)
→鈴(ながとやさん)→クマのぬいぐるみとヨーヨー
(M.Roman2さん)→バッグ(崇文堂さん)
【グループ3】
シール→ピンクのビニール袋(商店街を歩いていたHさん)
→よーじやのあぶら取り紙(商店街を歩いていたOさん)
→ポケットティッシュ(商店街を歩いていたYさん)
→ペンセット(南山堂薬局さん)→ボールペン(たけまさしょうてんさん)
→コマ(Mロマンさん)→ウェットティッシュとメッセージカード
(商店街を歩いていたHさん)→自由帳(マックスゲームさん)
→メモ帳とボール(ながとやさん)→せんぷうき(杵屋さん)
※子どもの記録したワークシートより名前を掲載させていただきました。
間違い等ございましたら、ご容赦くださいますようお願い致します。
2018年03月23日
とり+かえっこ
2月11日に「とり+かえっこ」が開催されました。
「とり+かえっこ」とは、「まだ使えるけど、もう使わない。
でも誰かに使ってもらいたい」そんなおもちゃを持ってきて
ポイントに交換し、代えたポイントで他のお友達の持ってきた
おもちゃを買うことができるプログラムです。
開催一週間前から、子どもたちの店長の活動が始まります。
毎日、15時から17時まで、集まった6~11人で、ゲームコーナーや
内装の準備を行います。ゲームコーナーの内容を決めるときは、
幼児~中高生までが楽しめる内容かどうかを考えながら、
他の店長さんと案を出し合いながら考えます。今回は、
「○×ゲーム」「輪なげ」などのたくさんの提案の中から、
ボールを箱に入れる「箱入れゲーム」と「モグラたたき」
「人間まちがい探し」の3つに!ハンドメイドショップは
小学校でやってきて楽しかったからという声で
「きらきらメダル屋さん」に決まりました。
ゲームが決まると、今度は、参加者の年齢別に、
「どう難しくする?」「ポイントはいくつにする?」
そんな風に店長同士で声をかけ合って、話を進めていきます。
「とり+かえっこ」で重要なのは、決定するのは子どもたち
だということです。ゲームの種類を決めるのも、
銀行でおもちゃの価値を決めるのも小学生店長です。
銀行の店長に自分の持ってきたおもちゃの素晴らしさを伝えたことで、
おもちゃの価値が上がり、ポイントが多くなることもあります。
「愛着があるけど、次の人に使ってほしい」そんな思いが店長に
伝わったからだと思います。
今回はたくさんのお客さんが集まり、
準備と当日の運営をした小学生店長は
張り切っていました。店長は、初めての人に受付で「とり+かえっこ」
の遊びの説明をしています。「わたしより上手」と2歳くらいの子の
お母さんにほめられた時は、次の人へ率先して説明していました!
午前中の準備から6時間近く店長をやりきった小学生の感想は、
「疲れた」という言葉ではなく、大盛り上がりだったオークション
への驚きと、1週間がんばった達成感から出た「楽しかった」の言葉でした。
4月以降は、新1年生も店長になれます。
当日の参加も合わせ、ぜひお楽しみにしていてください!!
(都築)
2018年03月01日
「おはなし会スペシャル」 ~ハッピーメロディのバルーンSHOW~
2月18日(日)、ハッピーメロディさんによる、
バルーンアートショーとパネルシアターが行われました。
風船芸とジャグリングが得意な「みどり」と歌がだいすきな
「ぴんく」の2人組による公演です。
最初は、「ドキドキわくわく風船SHOW(ショー)」。
バルーンアートで色が変わる剣や、ミッキーマウスと
ミニーマウスのリースづくりなどを披露していただきました。

つづいて、パネルシアターです。テンポのよい音楽に合わせて、
「ひよこちゃん」「鬼のパンツ」など、
さまざまな演目が行われました。見ていた子どもたちも、
一緒になって手をたたいたり、声を出して笑ったりと
大盛り上がりでした。そして、「ジャグリング刑事」の登場です。
盗まれたダイアモンドを取り返すため、ジャグリングで
怪盗に挑みます。警察犬(大きなトイプードルのバルーン)の
エサをお手玉のようにくるくると回したり、
ディアボロというコマで、怪盗の乗っている気球を破裂させたりと、
数々のジャグリングの技により、
みごとダイアモンドを取り返すことができました!
最後には、子どもたちも実際に風船を手にとって、
バルーンアートにチャレンジです。「割れそう!」
「こわいこわい!」とこわがりながらも、ひねってみると、
「あっ!できたできた!丸になったよ!」ねずみの顔の出来上がり。
さらにいくつか丸を作っていくと、耳が2つ、体が1つであっというまに
ねずみが完成しました。実はこのねずみ、ただのネズミではなく、
しっぽを引っ張るとぴょーんと飛び上がる飛びネズミでした。
「3・2・1、ぴょーん!」とみんなでネズミを飛ばして楽しみました。
麻布子ども中高生プラザでは、
子どもたちに豊かな情操を育む体験をしてもらうことを目的に、
年間を通して人形劇、紙芝居、読み語り、パネルシアターなどを楽しむ
「おはなし会」を実施しています。
そして、1年に数回は、より質の高いおはなしの世界を
子どもたちに提供するために、プロの方をお招きし、
「おはなし会スペシャル」を実施しています。
3月4日には、「わけちゃんのお楽しみげきじょう
~紙のペープサート あれこれ~」の上演、
3月20日(火)には人形劇団プークさんによる
「ハリネズミと金貨」の上演があります。
ぜひ、親子でお話の世界をお楽しみください!
(渡邉)
2018年02月27日
ALWAYS 4丁目の映画会
1月28日(日)に「ALWAYS 4丁目の映画会」
を行いました。当日はアリーナがどこか
懐かしい雰囲気に包まれた空間に変身しました!
17時から会場がオープンすると、いつもは飲食厳禁のアリーナ内ですが
この日は「港区青少年対策高陵地区委員会」の方々にご協力を頂き、
ポップコーン屋さんを出店しました!
ポップコーンの味が自分で選べたのもあり、
子ども達からは「おいしい!」との声が多く聞かれました。
17時半からの演芸大会には「南茶亭響輝」
(なんちゃっていひびき)さん (高校生)による落語(六尺棒)と
職員と学童クラブの保護者による「バルーンブラザーズ」
によるバルーンアートが行われました。
落語はほとんどの子が初めて聞く子が多く、
笑い声よりもみんな真剣に聞いていました。
バルーンアートでは、みんなで剣を作りました。
みんな上手に出来、大喜びでした!
そしていよいよ今回の作品『魔女の宅急便』の上映です。
16ミリ映画フィルムを映写機で上映しました。
16ミリフィルムには1コマ1コマ連続した写真を映写機にかけて見ると、
人間の目が物を見る仕組みと同じ仕組みになります。
ですからフィルムの映画は自然に滑らかに見えるという特徴があります。
上映前には「こんなに大きい機械でどうやって映画を映すの?」
と興味津々に見ている子も多く居ましたが、
映画会が始まると16ミリフィルムから聞こえてくる「カタカタカタ」
という音とともにざわざわしていた雰囲気が一瞬で静かになり、
みんな画面に吸い込まれていきました。
いすに座っている子はポップコーンを食べながら、
じゅうたんに座っていた子はごろごろしたり、
小さい声で友だちと話しながら見たりと各々の楽しみ方をしていました。
また映写機ならではのフィルムチェンジの時間があり、
普段の映画館ではなかなか見ることができないこともありました。
交換しているときは「どうやってやるのかな?」
と不思議そうな表情で見ていました。
今回の映画会はみんなで同じ作品を見て笑ったり泣いたりする事で
子どもの心に豊かな感情を育てたいという思いからこの企画しました。
1つ残念だったことは、映画会終了後に椅子の下や床に袋や食べこぼしが
散乱していました。
みんなで優しい気持ちに包まれた雰囲気を最後まで大事にしたかったです。
林(亮)
2018年02月15日
鬼と勝負だ!節分バトル
2月3日は節分でした。子どもたちに季節行事を楽しく感じて
もらうために、麻布子ども中高生プラザでは
毎年節分を行っています。みなさんのところには、
鬼はやってきましたか?麻布子ども中高生プラザにも
鬼がやって来て、みんなの元気や健康、
幸せのつまった元気だまを奪い取ってしまいました・・・。
このままでは、1年間、元気にたのしく過ごせない・・・!
なんとか元気だまを取り返したい!と、鬼に勝負を挑みました。
1つ目のゲームは鬼が島じゃんけん!
じゃんけんゲームで対決をして、鬼大将を目指します。
3回連続で小鬼たちに勝つことができると、
いよいよ鬼大将との対決です。
じゃんけんぽん!鬼大将に勝ったら、
元気だまを1つ取り返すことができます。
たくさん勝って、少しずつ元気だまが増えてきました!
すると・・・「やめやめ~!」
と強引にゲームを終了されてしまいました。ずるい鬼たちです。
そうして提案された次のゲームは、つなひき対決でした。
鬼7人(匹?)VS子どもたち全員(50人近く)!
鬼よりもこちらの人数が多いので、負けるわけない!
と思っていたのですが、手ごわい鬼たち。なかなか勝負がつきません。
「オーエス!オーエス!」とみんなで力をあわせて、
なんとか勝つことができ、鬼たちは悔しそうに退散していきました。
こうして2つのゲームに勝って、元気だまを取り戻したので、
みんなで豆を食べようとしたのですが・・・、なんと鬼たちが、
金棒を持って再び現れました!「まとめて喰ってやる~!」
とどなる鬼たちを前に、みんなで「鬼は~外!福は~うち!」
と豆をまきました。今度こそ鬼たちに完全勝利です。
一緒に鬼退治をしてくれたみなさん、ありがとうございました。
今年も1年、元気に楽しく過ごせる年になりますように・・・。
(渡邉)